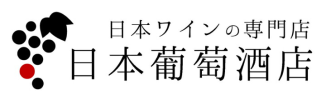ワインをおいしく楽しむ
トップページ > ワイン
ワインをおいしく飲むために

ワインについて
赤ワインには健康効果が認められるポリフェノールが多く含まれ、良質でコストパフォーマンスのいいワインが流通することで、幅広い層から愛されています。
酒屋さんのワインコーナーを見ると、ポリフェノールを他よりも多く含んでいることをキャッチコピーにしている赤ワインが多く見られます。
近年では日本のワインが世界的に認められ、ワイン人気に拍車がかかってきていますが、 ワインには実に多くの種類があり、同じブドウの品種でも、育つ土地の気候や土壌などの自然条件が変わると、違ったものが出来上がります。
このことテロワールという言葉で表します。
テロワールが違えば、同じ品種でも育つブドウに影響が出て、 そのブドウから作るワインにも個性の違いが出てきます。
ワイン プチトリビア1
![]() 甘くておいしい食べるブドウと、ワインになるブドウは同じもの?
甘くておいしい食べるブドウと、ワインになるブドウは同じもの?
日本の甲州やオーストラリアのサルタナなどのように、普通に食べているブドウをワインにしたものもありますが、
高級なワイン作りには向かないそうです。
ワインに大切な香味成分は皮のところに多く含まれていて、食べるブドウは皮が薄いので、
香り高いワインができないからです。
白ワインを作るマスカットも、食べている生食用のものからテーブルワインはできますが、
高品質なワインを造るときは、粒の小さい専用の品種を使うそうです。
ワインはいつごろから飲まれていたのか
ワインが造られ始めたのはいつ頃か
ブドウの木は約7000年前、西アジアのコーカス地方で栽培されていたのが分かっています。旧約聖書のノアの方舟が漂着して、初めてブドウ畑を開き、ワインを作ったとされている地、
アララット山とほぼ一致しているそうです。
ワインについての最古の資料として、紀元前2000年メソポタミアで書かれた『ギルガメシュ叙事詩』があります。
紀元前5000~4000年頃のことが書かれているとされていますが、この中にブドウから造られた酒を指す表現があるというのです。
最新の研究では、現在のイラクに当たるメソポタミア、シュメールのウルというところで発掘された紀元前3000年前に刻まれた粘土板にワインの記述があるそうです。
ブドウからワインを造るようになった始まりは、ブドウを保存しようとして偶然ワインを発見したという説と、
ブドウを搾って新鮮なブドウの汁を飲む習慣が一般化されるうちにワインが発見されたという説があるそうです。
ブドウは乾燥した土地や荒れた土地でも育ちやすかったので、広く栽培されていました。
ブドウの実は、内側に果汁があり、実の外側には自然酵母がついています。
収穫されたブドウが、何らかの形で皮が破れたり、人為的に絞ったりすることで、果汁と酵母が触れ合い、
発酵が始まったとしても不思議ではありません。
発酵酒としてのワインは、ブドウが育つところならば、自然と出来上がってしまうので、
それを利用し、ブドウの栽培を行い、ワインを製造し始めた可能性は十分考えられます。
そのためか、「人類最古のお酒」といわれることもあるそうです。
*微生物である酵母は、35億年前から地球上に存在していたと考えられています。
ウィキペディアによると、” 最古の酒とされている蜂蜜酒(ミード)は農耕が始まる以前から存在し、 およそ1万4千年前に狩人がクマなどに荒らされて破損した蜂の巣に溜まっている雨水を飲んだことが始まりとされている。 ”
とありますが、これはアルコール飲料との出会いであって、人類が造る酒といえるものなのかどうか、明記されておらず、
他を調べてみましたが、分かりませんでした。
ワインと人類の出会い
紀元前3000~1500年頃にはエジプトでもワインが飲まれていたようですが、王族など一部に限られ、広く庶民に広がるのは、紀元前1500年以降、ギリシャ・ローマに伝わってからといわれています。
 驚いたことに、古代エジプト人やギリシャ人は、ワインを水で割って飲んでいたようなのです。
驚いたことに、古代エジプト人やギリシャ人は、ワインを水で割って飲んでいたようなのです。今では考えられませんが、それだけ貴重だったのかも知れません。
また、船に水を積んでおくと腐ってしまいますが、ワインだと腐らないので水の代わりに使われ、それとともにワイン造りが各地で盛んになったものと思われます。
紀元30年、キリストが最後の晩餐で「このパンはわが肉、このワインはわが血」という言葉を残し磔刑に処せられましたが、キリスト教の普及とともに、キリストの血であるワインも各地に広まる一因となりました。
人間とワインのかかわりついて、面白い伝説があります。
ペルシャのシャムード王が、収穫を終えたブドウをいつでも食べられように貯蔵室に保存しておきました。
貯蔵室には番人を立てて置いたのですが、ある日その番人が倒れてしまいました。
壺の中でブドウが自重でつぶれ、下のほうの汁が自然に発酵して炭酸ガスが発生、貯蔵室に充満して酸欠になり、
番人が倒れてしまったのです。
当時はそのようなメカニズムはわかっていなかったので、ブドウが毒に変わったと恐れました。
ちょうどその時、シャムード王の愛妾の一人が王の不興を買い、
前途を悲観して、貯蔵室に行って毒と化したブドウの汁を飲んで死のうとしました。
しばらくすると彼女が戻ってきて、王の前に出ると、美しい声で歌い始め、かろやかに踊り出しました…
それを見たはシャムード王は喜び、彼女は一命をとりとめました。
そして王は、その奇跡の液体を、いつも宴会に供するようになりました。
![]()
ワイン プチトリビア2
![]() バイタリティの語源は、ブドウでした。
バイタリティの語源は、ブドウでした。
元気で、疲れ知らずに活動する人のことを、バイタリティ(vitarity)にあふれた人と言ったりします。
活力のもとはヴァタミン(vitamin)ですが、
その語源が、ラテン語のブドウとブドウから造った酒を意味する言葉にあります。
ラテン語でブドウはヴィティス(vitis)、ブドウから造った酒をヴィヌム(vinum)といいます。
これが英語のワイン(wine)、フランス語ではヴァン(vin)、ドイツ語がヴァイン(wein)、イタリア語、
スペイン語になるとヴィーノ(vino)、ポルトガル語ではヴィーニョ(vihno)になりました。
ビタミンのアミンは、ビタミンが発見されたときの物質がアンモニアからできる化合物で、ワインや生命ににつながる言葉、” Vie ” とつけて、ビタミンとされました。
![]()
周防の領主大内義隆に献上されたのが最初と伝えられています。
キリスト教にとって赤ワインはキリストの血とされていますから、儀式には欠かせません。
ザビエルも当然持ってきていたでしょうから、それを日本の大名たちに布教のために贈ったと考えられています。
ということは、織田信長も豊臣秀吉も飲んでいたに違いありません。
当時は赤ワインは珍陀(ちんた)酒といわれていたそうです。
チンタはポルトガル語で赤を意味し、「珍陀」を当てたものです。
江戸時代にもワインは飲まれていた
『徳川実記』寛文8年の記事の貢物の中に「沈多酒(ちんだしゅ)」の文字があるので、江戸城内にワインが貯蔵されていたことになります。ただこれが南蛮渡来のものか日本で作られたものかははっきりしていないそうです。
この時代、日本でも葡萄酒作りがなされていて、『本朝食鑑』という本にその製法が記されているそうです。
ただし、そこに記されている方法ではワインと呼べるものはできず、
簡単にいうと、梅酒の梅の代りにブドウを入れるといったものだったようです。
シニアには懐かしい 赤玉ポートワイン
明治に入ると、赤玉ポートワインが店頭に並ぶようになりました。ワインではなく、着色甘味料入りアルコール飲料ですが、 戦後もしばらく売られていて、シニアの方で覚えている人も多いはずです。
しかしこれは日本だけの話で、ポートワインは、三大酒精強化ワインの一つといわれるブランドワインです。
ポートワインについて
ポルトガルのポートワインは三大酒精強化ワインの一つといわれ、他はスペインのシェリー、ポルトガルのマディラです。ポートは生産地の名前ではなく、港の名称です。
ポートワインが今のように有名になるのには、当時の国際情勢、フランスとイギリスの戦争が関係していました。
(残念なことですが、いつの時代も、戦争には文明の発展を促す効果があります。)
17世紀末ごろから英仏間の植民地覇権抗争が激しくなり、イギリスは対仏禁輸措置を取りました。
ところがイギリスはフランスのボルドーから多くのワインを輸入していましたから、
あっという間に供給量が不足してしまいました。
そこで代わりにポルトガルのポート港からワインを輸入したのです。
取引量が増えるにつけて、品質もどんどん向上し、やがて風味を増し、品質を安定させるためにブランデーを混ぜるようになりました。
当時は、ワインを保存しておくと、技術的に確立していないこともあって、酢になってしまうものも多かったようなのです。
ブランデーやアルコールを加え度数を上げることで、酒質が安定し、風味も増すので、その風習が定着し始めました。
品質が良くなることで有名になると、偽造品が出回るようになりました。
あまりのひどさに、ついに時の宰相がポートワインのブランドを守るために動き出しました。
ブドウの栽培地や栽培方法、醸造方法を定め、規制したのです。
ポートワインが三大酒精強化ワインの一つといわれるようになったのには、こういう歴史的背景がありました。
*酒精強化ワインについては「ウィスキー」の項で紹介します。
![]()
ワイン プチトリビア3
![]() ワインの瓶が上げ底になっているのは、どうして?
ワインの瓶が上げ底になっているのは、どうして?
瓶の形はいろいろあっても、どの瓶も底は凹になっています。
ワインは、倉庫に貯蔵します。
長く熟成されておいしくなるのですが、その間にタンニンや酒石もできます。
底が平らだと、グラスに注ぐときにこれらの澱(オリ)のようなものが混じりやすくなりますが、
上げ底になっていると、くぼみに沈殿していて外へ流れ出にくくなります。
見た目にもよくなるし、雑味が混じるのも防げます。
昔の人は、少しでもおいしいワインを飲むために、ちゃんと創意工夫を凝らしていたわけです。
プレゼントに最適/生まれ年のカゴ盛りワインセット
生まれ年のワインとワインを楽しむのに必要なグラスやワイン抜き、ランチョマットやコースターといった便利な小物をセットしてカゴ盛りのギフトセットに仕上げました。おしゃれな誕生日プレゼントや、お祝いの贈り物として最適です。
 生まれ年でカゴ盛りワインセットを探す
生まれ年でカゴ盛りワインセットを探す家飲みセット
![]()

【超希少限定!!超入手困難】
独占輸入! 他では入手できません!
あの超人気天才醸造家[ベン・グレッツァー]の造り出す極上満点セット!
うまいお酒の最高の相棒、おいしいグルメ
全国にまだまだ知られていない隠れた“おいしさ”がいっぱい
ロス削減 - ”もったいない” を減らすサイト
 賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、
賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、まだ食べられるもの、使えるものをお買い得価格で提供するSDGsなサイト。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9294c0.9d0ae1f2.1c9294c1.1c5d2e24/?me_id=1191419&item_id=10003676&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwac%2Fcabinet%2Fspecial%2Fienomi_zwiesel2.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9294c0.9d0ae1f2.1c9294c1.1c5d2e24/?me_id=1191419&item_id=10003675&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwac%2Fcabinet%2Fspecial%2Fienomi_zwiesel.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9294c0.9d0ae1f2.1c9294c1.1c5d2e24/?me_id=1191419&item_id=10003674&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwac%2Fcabinet%2Fspecial%2Fienomi_riedel2.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9294c0.9d0ae1f2.1c9294c1.1c5d2e24/?me_id=1191419&item_id=10003672&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwac%2Fcabinet%2Fspecial%2Fienomi_zalto2.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9294c0.9d0ae1f2.1c9294c1.1c5d2e24/?me_id=1191419&item_id=10003671&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwac%2Fcabinet%2Fspecial%2Fienomi_zalto.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c896686.e06cc798.1c896687.263ec4c2/?me_id=1277065&item_id=10004662&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fissyusouden%2Fcabinet%2F20000033set-t1.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a617353.5baf91c5.1a617354.f4797f34/?me_id=1237117&item_id=10013980&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmywineclub%2Fcabinet%2Fshohin27%2F7793124.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)