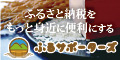ワインに含まれる健康や美容に効果のある成分

赤ワインブームが起きましたが、ほかにはどのような健康効果があるのでしょう。
また、赤ワインだけで、白ワインに健康効果は期待できないのでしょうか。
それらについて、わかりやすくまとめてみました。
ポリフェノール
ポリフェノールは、植物に含まれるタンニンなどの成分の総称で、約4000種あるそうです。ワインはブドウに含まれている成分のほとんどをその中に取り入れているので、
多くのミネラル、ビタミン、ポリフェノールなどが含まれていています。
ブドウに含まれるポリフェノールのおもな働きは、
活性酸素を除去し、悪玉コレステロールを減らします。
また、有機酸も多く含まれていて、腸内細菌群のバランスを整え、ビフィズス菌などの善玉菌を増やす効果あるそうです。
その結果、動脈硬化、高血圧、ガンなどの予防効果が期待されるといわれています。
ブドウには、レスベラトロールというポリフェノールあり、 ガンに効果のある物質が含まれていて、現在、ガン治療薬としての研究開発も進められているとのことです。
しかも、ワインの醗酵過程で、レスベラトロールが倍加されることがわかってきました。
ブドウをそのまま食べるよりは、ワインで飲んだ方が、より多くの効果が期待できます。
また、ブドウの果肉には、学習や記憶に関わる脳神経ホルモンの働きを助けるペプチドも含まれています。
ポリフェノール以外の成分
ワインにはほかに、多くのミネラル、ビタミン、有機酸などが含まれています。ミネラル
・マグネシウム / 不足すると動脈硬化、高血圧になりやすくなります。
・カルシウム / 歯や骨を丈夫にし、健康な血液造りに役立ちます。
・カリウム / 脳の血管を強くします。
・イオウ / 肝機能を高めます。
酒石酸、乳酸などの有機酸も多く含まれ、腸の働きをよくする効果があるといわれます。
酒石酸は、コルクを抜いたときに、コルクの裏に結晶のようにつくこともあるので、どいうものか見ることができます。
胃で吸収されずに腸まで行き、腸内細菌のバランスを整え、ビフィズス菌などの善玉菌を増やして腸内環境をよくします。
免疫力がアップし、便通なども改善される効果が期待されます。
低糖質
ワインは低糖質なので、糖分を気にしている人にお勧めです。
2015年の文部科学省のデータでは、 100g当たり、赤ワインは1.5g、白ワインは2.0gです。
日本日本酒が3.6~4.9g、ビールは3.1~4.9gほどなので、ワインの糖質がいかに少ないかが分かります。
赤ワイン
ブドウの果皮や種子には、カテキン、 フラボノイド、タンニン、アントシアニンなど、多くのポリフェノールが含まれています。赤ワインには、 ブドウを丸ごと発酵・熟成させるので、果皮と種子を除いて発酵させる白ワインに比べると、多くのポリフェノールが含まれています。
健康や美容によいといわれるポリフェノールですが、お茶などをはじめ、いろいろな食品に含まれています。
赤ワインには、緑茶の数倍近く含まれているそうです。
また、赤ワインに含まれるポリフェノールは分子量が大きく、そのままでは腸で吸収されません。
この大きな分子のポリフェノールを、腸内の善玉菌が餌にして、小さく分解してくれます。
小さくなったポリフェノールは、体内に吸収されやすくなります。
餌が多くなれば善玉菌も増え、それにより、ポリフェノールの効果も促進されることになります。
バード大学医学部の研究チームが、赤ワインのポリフェノール成分のレスベラトロールに、寿命を延ばす働きがあると発表しました。
また別の研究チームが、人の寿命の左右するテロメアDNAの寿命を延ばす助けをすると報告しています。
もちろん、これらの研究報告を踏まえて、赤ワインを飲んでいれば大丈夫だというものではありません。
ワインはほとんどが水とアルコールで、残りのほとんども糖分と酸で、これらの成分は極微量含まれているにすぎません。
ポリフェノールを多く摂るために、飲むワインの量を増やせば、ほかのアルコールと同じように、害のほうが多くなります。
白ワイン
白ワインに含まれるポリフェノールは、 赤ワインの半分から数分の1程度ですが、白ワインのポリフェノールは、量は少なくても、その効果では赤ワインに劣らないそうです。
白ワインに含まれるポリフェノールは、赤ワインと違い分子が小さく、カラダに吸収されやすくなります。
また、骨を強くする効果や、ヘリコバクターピロリ菌の抑制や、整腸効果も期待されます。
最近、品質の良さが世界的に認められ、日本国内でも人気が出てきた日本オリジナルの甲州種のブドウは、ポリフェノールの含有量が多く、アミノ酸も豊富に含まれていて、健康効果が期待されているといいます。
白ワインには酒石酸、リンゴ酸などをはじめとする有機酸が多く含まれていますが、これらの酸には強い殺菌力があることが知られています。
赤痢菌、サルモネラ菌、大腸菌など、食中毒を引き起こす菌に特に有効で、
サルモネラ菌を10分、大腸菌は20分で、10万個以上の菌が数個にまで減少するそうです。
殺菌力に関しては、赤ワインの半分の量で同等の殺菌効果が得られるそうです。
殺菌力の強い白ワインを、生牡蠣などの魚介類と合わせることが多いのは、昔の人が経験的に知っていたからかもしれません。
白ワインには、カリウムも豊富に含まれています。
カリウムには利尿効果があるので、尿と一緒に体内からのナトリウム(塩分)を排出することで、高血圧の方も効果が期待できます。
白ワインの健康効果を上げるためには、いつ、どれくらいの量にしておくのががいいのかというと、
専門家の意見では、食前酒として、ワイングラス1~2杯を、食事と一緒にとるのがおすすめだそうです。
スパークリング ワイン
スパークリング ワインの健康効果は、白ワインから造るわけですから、白ワインと同じようなものになります。ただ、酵母や糖分を加えて瓶内で二次発酵させる製法上だと、ポリフェノールのほかに、 アスパラギン酸、ヒスチジン、リジンといった多くのアミノ酸成分が抽出されます。
炭酸が加わると吸収が速くなりますし、いろいろな成分が増えているので、白ワインより健康効果は高いといえます。
酸化防止剤について
酸化防止剤が入ったワインというと、人工物が入っているようなイメージが強くなりますが、ワインに使われる酸化防止剤は亜硫酸塩で、ワインの酸化を防ぐほか、殺菌効果、果皮や種からの成分の抽出を助ける働きがあり、昔から使われてきました。
実際は食品添加物で、高級ワインにも入っています。
長期間かけて熟成させるワインは、その期間中にワインの劣化を防ぎ、味わいをふくよかにするために、微量の亜硫酸塩を食えます。
特に赤ワインの熟成では、亜硫酸塩がないと赤色の成分、渋み、コクなどが失われてしまいます。
使われる量も、人体に影響が出るほどの量ではありません。
酸化防止剤無添加ワインとビオ ワイン
酸化防止剤の入っていない無添加ワインとビオワインは、全く別のものです。酸化防止無添加ワインは亜硫酸塩を加えていないワインで、ビオ ワインは原料に有機栽培したブドウを使ったワインのことで、オーガニックワインとも呼ばれ、化学肥料、除草剤、 殺虫剤などを一切使用しない農法によるブドウで造られます。
ビオ ワインについては、ワインの分類をご覧になってください。
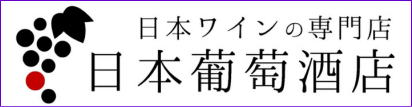

発酵を終えた造りたてのワインや、ナチュラルな風味をそのまま残した、無濾過のワイン。
ワイナリーの中の人しか味わえなかったその美味しさをお届けします!

![]()
全国各地の「ご当地の美味しいお酒」と「ご当地自慢のグルメ」セット。
北海道から沖縄まで、「ワイン&チーズ」「日本酒&ふく」「芋焼酎&鶏炭火焼」など、
100セットを超えるランナップで、満足度120%!
![]()
うまいお酒の最高の相棒、おいしいグルメ
全国にまだまだ知られていない隠れた“おいしさ”がいっぱい
ロス削減 - ”もったいない” を減らすサイト
 賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、
賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、まだ食べられるもの、使えるものをお買い得価格で提供するSDGsなサイト。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ad9d9d5.456cbea5.1ad9d9d6.1d34b4ec/?me_id=1295961&item_id=10010176&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fliquor-boss%2Fcabinet%2F03382778%2F04358998%2F06528031%2Fimgrc0174377673.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1dac9c5d.582bac32.1dac9c5e.46427adc/?me_id=1283706&item_id=10003665&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoryomuryo%2Fcabinet%2Ffin%2Ffin-4976652007185.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1caba6fc.c428f32c.1caba6fd.74d27ef5/?me_id=1195685&item_id=10002062&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fveritas%2Fcabinet%2Ft1%2Fcbd8_touroku.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cab6176.b11706f5.1cab6177.3232ba02/?me_id=1194184&item_id=10013545&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkbwine%2Fcabinet%2Fgazou8%2Fwhite6-157.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d9f37e4.cbf88f91.1d9f37e5.fc2439e8/?me_id=1336754&item_id=10000295&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-yamanashi%2Fcabinet%2Fproduct%2Fwine%2Fwine-sjun%2Fsj-0005.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1dac9ec1.3dbb9132.1dac9ec2.d18fdb82/?me_id=1234995&item_id=10000242&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnamawine-m%2Fcabinet%2Fy-wine%2Fsupakuringuset.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cb67719.c3dcfa13.1cb6771a.bd3ea97c/?me_id=1308603&item_id=10001147&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Finter-mic%2Fcabinet%2Fgoodsimg%2F80%2F10001440_7.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1acf54d1.b82d5149.1acf54d2.cb9a87e5/?me_id=1204206&item_id=10001033&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhiguchiwine%2Fcabinet%2Fsinki30_12%2Fs-0079_new2.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)