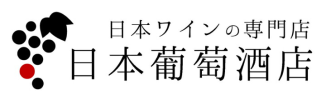ワイン、風味の違いと選び方

誰かに贈る場合は、相手の好みに合ったものがいいのでしょうが、
どれが相手の好みにあうのか、ラベルだけでは見当がつきません。
好みに合わせてワインを選ぶヒントがわかれば、より選びやすくなります。
そこで、それぞれの違いによって、どのような風味の違いが出るのか、参考になる目安を紹介します。
![]()
ブドウの違いによる、味わい
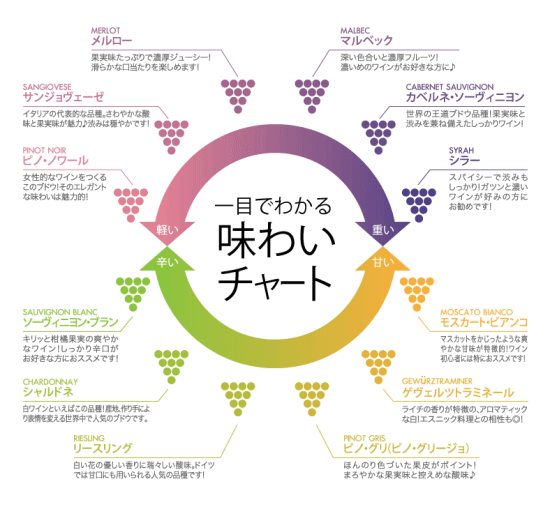
ワインの風味が異なるわけ
ワインにはいろいろな味わい方があります。風味や香りを楽しむ、熟成度、フルーティーさ、余韻などを味わう、とそれぞれの好みにあったワインが楽しめます。
ワインのもとのブドウが育つ環境、例えば斜面か平坦地か、日照量、気候、地質や水はけ状態などが違えば、
同じ品種のブドウでも、みずみずしさや味、香りが異なって育ちます。
また、栽培方法や収穫の時期をずらしてみたり、酵母や発酵の仕方を研究したりとか、
ワインの生産者たちは、自分たちのワイン造りの目標を定めて、よりおいしいワイン造りのために努めているからこそ、
消費者は、様々な香りや味のワインが楽しめます。
香りの違い
ワインの香りには、「アロマ」系と 「ブーケ」系があります。アロマ
ブドウそのものからくる香りで、第1アロマといい、発酵しているときに生まれる香りを第2アロマといいます。
アロマティックといわれるワインは、第1アロマによるものです。
ブーケ
木樽や瓶の中で熟成するときに生まれる香りをブーケといいます。
青草や腐葉土、動物系の香り、ヴァニラや木樽の木の香り、ロースト香などがあります。
多いのが果実や花などの植物、スパイス、ナッツなどがありますが、
動物やネコのおしっこ、ヨードや生ゴム、ワックスなどにたとえられることもあります。
ネコのおしっこなど、どうしてもおいしそうとは思えませんが、文化の違いによるのかもしれません。
ワインの色で選ぶ
色の違いによる風味の違い
ワインは色によって大きく3つに分けられますが、それそれについても濃淡があり、その特徴を抑えておくことは、ワイン選びの時の助けになります。
赤ワインは、淡い色なら渋みが少なく、フレッシュ感があります。ブドウの品種としては、ピノ ノワールなどがおすすめです。
色が濃くなるほど熟成が進んでいるので、渋みが強く、濃厚な味なり、熟成した風味になります。品種は、カベルネ ソーヴィニヨンなどがおすすめです。
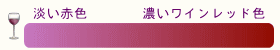
白ワインは、無色に近い方が酸味が強く、辛口でフレッシュ感があります。
濃くなるほど酸味が少なく、重厚な味わいで、熟成度が感字られます。甘口で、複雑な風味になります。
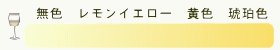
ロゼは、製法の違いが色に影響します。
淡い色のロゼは、酸味が強く、新鮮な味わいで、渋みは少なくなります。
濃い色になると、酸味は薄くなり、渋みが増し、濃厚な風味になります。

ワインの味わい
ワインの味わいを構成する骨格となる要素は、お酒ですから、基本はアルコールです。アルコール度数が高いと、ワインに厚みが加わります。
ワインの味わいを決めるものは、他にもいくつかありますが、これらのバランスが良いものがおいしいワインになります。
甘味
ワインに残っているか糖分が甘味になります。
甘味は味わいを濃厚に感じさせ、まろやかさも作ります。
アルコール度数が高いものは発酵が進んでいるので糖分は減り、辛口になります。
度数が低いものは甘口になりますが、酸味や苦味が強いと辛く感じやすい傾向がありますので、一概に糖分だけで甘辛の違いはいえないようです。
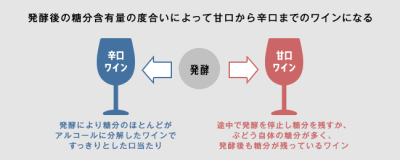
赤ワインは糖分を残さないように発酵させることが多く、甘口・辛口の違いは基本的にはありません。
ただ、フルボディの重めのワインで、辛口を表示しているものもあります。
果実味
ブドウしか使わないワインは、原料となるブドウ品種のフルーティーさや果実の風味も大きな要素になります。
果実味が豊かに凝縮されていると、ボディに厚みが出ます。
苦味
タンニンやポリフェノールに由来していて、キレの良さやシャープさになります。 しっかりした苦味があると、コクとして感じられることもあります。
酸味
果皮や種子にあるタンニンに由来していて、酒石酸、リンゴ酸と、発酵によって乳酸にもなります。特に白ワインでは、酒石酸とリンゴ酸が爽快感やシャープさになり、乳酸は赤ワインに含まれ、やまろやかさを生み出します。
渋み
赤ワインや白ワインに含まれる成分で、果皮や種子にあるタンニンに由来しています。渋味は味覚というより、辛味と同じように刺激物質といえ、「キメが粗い」「キメが細かい」といった言葉で表現されることがよくあります。
早飲みタイプと熟成タイプの違い。
ヌーヴォーのように造ってすぐに楽しむのが早飲みタイプで、長期間熟成させることで飲みごろになるのが熟成タイプです。
種類によって飲み頃は異なりますが、
一般的に、早飲みタイプは、アルコール度数が高く、果実味が濃いとパワフルなワインになります。
熟成タイプは、ワインの持つ各要素が時間を経ることによって落ち着き、成熟した風味が感じられます。
フレッシュさやフルーティーさでさわやかな飲み口のタイプは、長期熟成させずに、1~2年が飲みごろになります。
各種ヌーボーやロゼ、手ごろな価格のスパークリングワインに多くあります。
長期熟成させてから味わうワインで、5年以上、長いものになると、50年、中には100年近くになるものもあります。
カベルネ ソーヴィニヨンや、比較的高価な赤ワインに多くあります。
ポピュラーなワインに多く、3~10年くらい熟成させたものが飲みごろになります。
ボルドーのメドックや、ブルゴーニュの白ワインなどがあります。
ブドウの品種による味の違い
ブドウの品種によっても、違いが出てきます。同じ品種でも、ヨーロッパとアメリカの違いが出て、ヨーロッパ系はワインらしさが強く、アメリカ系はよりまろやかでフルーティーになります。
品種の違いについては、ブドウの品種による違い を参考にしてください。
赤ワイン
赤ワインは渋味や苦味が味わいを造ります。渋味や苦味が強い品種から示すと、
カベルネ ソーヴィニヨン ➡ メルロ ➡ ピノ ノワール ➡ ガメイ ➡ マスカット ベリーA
白ワイン
白ワインは酸味や果実味が特徴で、ブドウの品種によって違いが出るのは当然ですが、同じ品種でも産地よって味わいの違いが出てきます。酸味などの強い品種順では、
シャルドネ ➡ ソーヴィニヨン ブラン ➡ リースリング ➡ ミュスカデ ➡ 甲州
![]()
同じ金額くらいのワインを品種別、生産地別に飲み比べてみると、好みに合うワインを見つけやすくなります。
ワイン飲み比べ
一本一本飲んでいては、違いがよくわかりません。飲み比べてみて、はっきり味の違いがわかります。
ワイン好きの仲間内での集まりに、それぞれ飲み比べて味の違いを確かめるのも、大いに盛り上がります。
さっぱりしたフルーティーなワイン
風味とコクのあるワイン
独特な風味のあるワイン
オレンジワインはオレンジではなく、ブドウから造られます。だからワインと呼ばれます。
白ワインと赤ワインの造り方をミックスさせたような醸造方法で、 口当たりの良い、フレッシュ感の強いワインになります。
そして特徴は、どんな料理にも合う、料理を選ばない風味から、 最近、ワイン好きの間にも人気が出てきています。
東欧のジョージアで造られていたワインでしたが、
隣接するイタリアのフリウリ ヴェネツィア ジュリアの白ワインの銘醸地にその製法が取り入れられ、世界的に知られるようになり、今ではいろいろな土地で醸造されるようになりました。
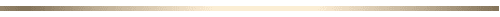
うまいお酒の最高の相棒、おいしいグルメ
全国にまだまだ知られていない隠れた“おいしさ”がいっぱい 
ロス削減 - ”もったいない” を減らすサイト
 賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、
賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、
まだ食べられるもの、使えるものをお買い得価格で提供するSDGsなサイト。
![]()
成美堂出版、木村克己監修「ワインの大事典」
新星出版社、木村克己「ワインの教科書」
このページは、主に上の3著を参考させていただきました。
図版や写真も多く、より詳しくワインについて知りたい方にはお勧めします。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/39c1cff0.ed832128.39c1cff1.932e548a/?me_id=1396110&item_id=10000137&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbest-wine%2Fcabinet%2Fimgrc0086193774.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca89165.644ce042.1ca89166.1f318597/?me_id=1213315&item_id=10007654&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fco2s%2Fcabinet%2Fitem%2F201903%2F61004207_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/26185521.1f3b39e9.26185522.b415ee09/?me_id=1215796&item_id=10000384&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fedelwein%2Fcabinet%2Fseries%2Ftknew%2Fnewhtaw.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cb6513c.07428ed5.1cb6513d.5d2442f9/?me_id=1247474&item_id=10001249&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftochikame%2Fcabinet%2Fit3%2F1091000025it005.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca876f6.a282e13f.1ca876f7.5bc1f930/?me_id=1313045&item_id=10003661&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2F06694665%2F06873258%2Fimgrc0075792724.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca88d0d.e08dcfa3.1ca88d0e.3f2f36dd/?me_id=1201918&item_id=10030731&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenoteca%2Fcabinet%2Fshohin_images_7%2F0901307503b9.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a617353.5baf91c5.1a617354.f4797f34/?me_id=1237117&item_id=10017246&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmywineclub%2Fcabinet%2Fshohin32%2F7789783.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca7c8d5.b4226696.1ca7c8d6.529d868e/?me_id=1211583&item_id=10006639&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyamagatamaru%2Fcabinet%2Fgoq002%2F7107_1.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9323c2.fc2567c7.1c9323c3.1b5d50d5/?me_id=1195995&item_id=10004299&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftsutaya%2Fcabinet%2F06547887%2F07443675%2F20200311_230129.gif%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1acf54d1.b82d5149.1acf54d2.cb9a87e5/?me_id=1204206&item_id=10004889&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhiguchiwine%2Fcabinet%2Fset150%2Fimg57658418.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ae48547.c6a93f68.1ae48548.7f587295/?me_id=1203934&item_id=10004492&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnishiura-wine%2Fcabinet%2Fset%2F4492.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1acf54d1.b82d5149.1acf54d2.cb9a87e5/?me_id=1204206&item_id=10010781&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhiguchiwine%2Fcabinet%2Fsinkigazouh30%2Fw36981_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1acf54d1.b82d5149.1acf54d2.cb9a87e5/?me_id=1204206&item_id=10010538&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhiguchiwine%2Fcabinet%2Fsinkigazouh30%2Fw36787_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9012f7.ffd8594d.1c9012f8.f92869b4/?me_id=1358263&item_id=10006775&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fukigoods%2Fcabinet%2Fwb003%2F1600002001013.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9012f7.ffd8594d.1c9012f8.f92869b4/?me_id=1358263&item_id=10016087&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fukigoods%2Fcabinet%2Ftam01%2Ftam017%2F1900004001029.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ac40bc1.f63a094e.1ac40bc2.dd64eb1e/?me_id=1224100&item_id=10007582&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fledled%2Fcabinet%2Fimg002%2F1-br-albia-rose_s.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1aa1442b.1c2384a7.1aa1442c.5c759938/?me_id=1213379&item_id=10010412&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftamaki-web%2Fcabinet%2Fdragee04%2Fimg62945435.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ae5be6d.dcc2200e.1ae5be6e.a730745c/?me_id=1196405&item_id=10077474&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoscana%2Fcabinet%2Fw_vt008%2F10079132-16.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d704ef5.15667597.1d704ef6.3283c768/?me_id=1194630&item_id=10020391&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fk-wine%2Fcabinet%2F05470369%2Fimgrc0075082335.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1aa1442b.1c2384a7.1aa1442c.5c759938/?me_id=1213379&item_id=10034876&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftamaki-web%2Fcabinet%2Fdragee14%2F18090306.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c929ae0.69d20c05.1c929ae1.67393753/?me_id=1200312&item_id=10032528&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwineuki%2Fcabinet%2Ftam01%2Ftam009%2F0105003000528_01.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/39c211c6.c8d1749c.39c211c7.1ce4a067/?me_id=1343187&item_id=10001653&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flamuno%2Fcabinet%2Fset%2Fimgrc0088385600.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)