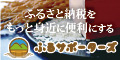ビールの味わいは、どこにあるのか

なぜ、それほど日本人の心をつかんでいるのでしょう。
味、香り、それとも喉ごしでしょうか。
広島にある、行列に並んでまで飲みたいビール専門のお店のマスターは、こう言います。
「見た目」「口当たり」「のど越し」「味わい」をあげ、
なによりも大事なのは、「泡の口当たりと触感だと思います。」
福沢諭吉の「西洋衣食住」に、
『その味至って苦けれど胸襟(きょうきん)を開くに妙あり』
とあります。日本人が好んだのは、今も昔も、爽快感だったようです。
![]()
終戦間もない1940年、何とも可笑しなビール裁判が始まりました。
「ビールの泡が多すぎる」と、ビアホールが訴えられたのです。
泡によって、ビールの量が減っている。泡は料金に含まれないもとでも思ったのでしょうか。
ビアホール側の主張は、「泡もビールのうちである。」でした。
裁判には鑑定人として、酒を研究している坂口謹一郎博士が呼ばれ、泡の分析結果を報告しました。
それによると、糖分、タンパク質、アルコールとも泡のほうが多いというものでした。
この結果は裁判官に受け入れられ、
判決は、ビールには15~30%の泡があってもいいとし、無罪になりました。
![]()
ビール プチトリビア
日本初のビア ホール
1899年(明治32年)7月。新橋寄りの京橋に開店しました。
「恵比寿ビール」を飲ませ、大盛況で、1日800人の客でにぎわったといいます。
この成功により、ビアホールはいくつも作られ、ビールが広く飲まれるようになりました。
これにより、ビールは市民権を得たといえます。
ビールの泡 / 成分と役割
ビールの泡は炭酸ガスの気泡でできています。しかし、ほかの炭酸飲料のように、すぐに消えてなくなることはありません。
この泡持ちの良さはビールの特徴ですが、周りの泡を強くしているのは、麦芽のタンパク質とホップの苦み成分が付着しているからです。
泡がビールをおいしくしてくれているのは、炭酸ガスが飛散したり、ビールが空気に触れて酸化するのを防いでいることです。
いわば、泡で蓋をして、おいしさを逃がさないようにしていることになります。
ビールをおいしく飲む注ぎ方
広島にある行列のできるビール店のマスターは、3通りの仕方でビールを注ぐそうです。- 1度注ぎ / ビールをグラスにぶつけるように、一気に勢いよく注ぎます。粒の大きいはじけるような泡が、心地よい刺激となって喉を通り過ぎる爽快感が味わえます。
- 2度注ぎ / 1度注ぎより強く注ぎ、グラス一杯にします。1~2分落ち着かせ、泡が半分位になったころビールでもう1度泡立たせます。フワーとした泡になればOKです。爽快感、味わいなどのバランスがよくなります。
- シャープ注ぎ / 炭酸を逃がさないようにゆっくり注ぎ、次に粒が見えない位細く注いぎます。なめらかで優しい泡と炭酸が同時に感じられます。
プロの技と専用のサーバーがあるからできることですが、
家庭での味わい方は、1度注ぎと、3度注ぎがあります。
試してみて、好みに合った方を選ぶといいでしょう。
 1度注ぎ / グラスを斜めにして、下から 1/3 当たりの壁面にビールを注ぎます。この時、底に向かってビールが渦を巻くように注ぎます。
1度注ぎ / グラスを斜めにして、下から 1/3 当たりの壁面にビールを注ぎます。この時、底に向かってビールが渦を巻くように注ぎます。注ぐスピードを保ちながらグラスを立ててゆき、上面に1cmの泡を作ります。
酸味や苦味が比較的強く感じられます。
3度注ぎ / (1) グラスの上、20~30cmのところから勢いよくビールを注ぎます。グラスが泡でいっぱいになったら、ビールと泡が5:5蔵になるまで1分くらい落ち着くのを待ちます。
(2) ゆっくりと注ぎ、泡が1cmくらいこち上がったら止めます。細かい泡が多くなるので、泡とビールが3:7くらいになるまで、2~3分はそのままにします。
(3) 泡がグラスから2cmくらい盛り上がるまで、静かに注ぎます。クリーミーな泡になっていれば成功です。
3度注ぎは、酸味や苦味がまろやかに感じられます。
缶ビールはグラスに移し替えてから
缶や瓶ビールは、詰めるときに炭酸ガスを注入しています。缶ビールはグラスに移し替えた方が、炭酸が程よく抜けるので、ビール本来の味が楽しめます。
ビールの飲みごろの温度
暑いときにキンキンに冷えたビールを飲むのは何とも爽快ですが、冷たいものであればあるほど人の味覚は鈍くなります。また人の好みはいろいろありますから、何度が最適という答えはありません。
ただ、一般的にいわれていることは、軽快な刺激的タイプのビールはやや低め。
芳醇な味わいタイプは、やや高めの温度で、といわれています。
また外気温によっても変わり、気温が35℃くらいの時は6℃前後、
25℃くらいの時は10℃前後、
15℃くらいの時は10~15℃くらいが適温といわれています。
![]()
人によっては、泡も立てない方がおいしいという人もいます。
ビールとグルメ
ワイン王国フランスでは、食事とワインは切り離せません。料理にあったワインを選ぶことは、とても重要なことで、ソムリエという専門職までいます。く料理とワインのペアリングを、マリアージュ(mariage)といいます。日本語にすると、「結婚」を意味します。
とても意味深な言葉です。相性がピッタリなら、これほど幸福なことはありませんが、最悪なら、あまり想像したくない結果になります。
クラフトビールのような地域の特性をいかしたビールにとっての最適なマリアージュは、当然、その地域の特産品との組み合わせです。
各地にそれぞれのペアリングがありますが、ここでは、岩手県の三陸を紹介します。
三陸のカキを使用した贅沢な黒ビール!いわて蔵ビール 牡蠣のスタウト
牡蠣のスタウトは、牡蠣の身と殻を使って醸造した濃厚な黒ビールで、岩手三陸広田湾特産の牡蠣の身と殻を両方使用して造り、濃厚でありながらさっぱりとした後味が楽しめる、絶妙なおいしさのビールです。牡蠣は、三陸町から生産者直送のものを紹介します。
フローズンビール、ホットビール
フローズンビール
キリンビールのレストランで開発されたそうです。アルコールは氷点が低いので、家庭の冷凍庫では凍にくいのですが、最近は日本酒や焼酎、ビールなども凍らせることができます。ガムシロを10%程度加えて凍らせるそうですが、いろいろな味のものを加えてカスタマイズするのも楽しいかもしれません。
クリームやチョコなどのトッピングも、いろいろ試せそうです。
ホットビール
北欧では寒い季節にビールを温めて飲む習慣があるそうです。レンジでOKですが、30秒から1分くらい、約50度くらいまでビールを温めます。
そのまま飲んでもいいのですが、角砂糖を入れて飲むのもいいそうです。
ただし、角砂糖を入れると、泡が噴出しますからご注意ください。炭酸ガスは温かい液体には溶けにくいので、少し刺激を与えると泡が噴出します。
ラガー系の色の薄いビールより、エール系の色や風味の強いビールのほうが向いているようです。
![]()
【ここでしか買えないクラフト酒!】
・商品化までに3年かけて完成させた梅酒や、バニラアイスにかけるために生まれた果肉酒等、
全国各地の酒蔵が造ったこだわりの逸品。
・「ほうじ茶のお酒」や「栗のお酒」といったような、珍しいお酒も非常に沢山!

1,900種類以上から厳選した、今一番楽しんで欲しい銘柄を、
毎回丁寧にセレクトしてお届けするクラフトビールの定期便。
![]()
元祖地ビール屋サンクトガーレン(クラフトビール)
大手ビールメーカーとは違うプレミアム感あるビール。 国際ビール審査会金賞受賞ビールをお届けします。

ビールを入れる器と味わいの関係
ビールを入れる容器といえば、今はガラス製がほとんどです。ビールは入れるグラスの形によって、味わいも違ってきます。
ドイツやベルギーでは、種類ごと、銘柄ごとに使うグラスが決まっているといわれます。
特にエールビールやクラフトビールのような香りを楽しみたいビールは、大きめのチューリップ型のグラスや、香りがたまりやすい膨ら荷を持ったグラスが使われます。
日本の場合はスピルナータイプが多いですから、顎を上げてグィッと飲めるような、
いわゆるヴァイツェングラスと呼ばれるものが向いているようです。
上部にふくらみを持たせてあるので、細かい泡がたまりたすくなっています。
特に、リーデルというブランドグラスメーカーは、日本人の好みに合わせた、日本限定のビールグラスを造っています。
グラスの厚み
苦味のあるビールでも、厚みのあるグラスで飲むと、甘みを感じやすくなります。厚手のグラスは、冷たさが長持ちします。飲み口が薄いグラスだと、苦みが強く感じられ、甘いビールのとき深みのある味わいが楽しめます。
ガラス以外の容器
金属二重タンブラーは、手に持っても、 熱さや冷たさが直に伝わって来ることがありません。持ちやすいばかりでなく、結露がしにくいので、 手やテーブルが濡れることもなく、
魔法瓶と同じ真空二重構造になっているので、冷たさが長続きます。
チタン製
チタンはイオン化しない金属なので、無味無臭、金属臭もありません。チタンで作ったタンブラーは、飲み物本来の味を活かし、美味しくまろやかにしてくれます。
またアレルギーフリーのやさしい素材でもあります。
ステンレス製
ステンレスは、バーベキューやアウトドアにも大活躍です。金属加工で有名な新潟県の燕三条で作られる製品は、内側の磨き方を工夫し、泡が小さくなるようにしているので、ビールの泡が細かくクリーミーになり、おいしさが引き立ちます。
![]()
錫製
錫はイオン効果が高く、抗菌性に優れ、 水を浄化し、飲み物をまろやかにするといわれています。金属でありながらどこか温かみを感じさせ、 見た目も涼やかで、銀のように酸化して黒くならず、 神器や茶道具としてよく用いられていたようです。
長く使っていると渋みが出てきてきなすが、 磨けばすぐに新品のようにきれいになります。
錫のタンブラーは、内側に細かな凹凸があって、 ビールを注ぐときめ細やかな泡になるので、一層ビールがおいしくなります。
![]()
木製
木製の良さは何といってもそのソフト感。熱伝導率が低く、熱を伝えにくいので、結露したり、熱くて持てなかったりということがありません。
竹製のタンブラーは、 一般的な木材と比べ、倍以上の強度を持ち、フィトンチッドを多く含むため、抗菌・脱臭性、
さらには癒しや安らぎを与える効果まで兼ね備えています。
ヒノキや杉製は、癒しとリフレッシュできる香りが楽しめます。
陶器製
ビアジョッキは釉薬をかけずに焼いていますから、内がツルツルになっていません。ビールを注ぐと泡が細かくクリーミーになります。
陶器は昔から日本人には馴染み深く、手触りや風合いはほかにはないもです。
保温性が高いので、冷蔵庫で冷やしておくと、冷たさを長く保てます。
ほかの容器について、より詳しくは ⇒「お酒をおいしくする器」
全国の地ビール(クラフトビール)
ご当地自慢の美味しいお酒とグルメのセット
おすすめビール ペアリング

ぜいたく晩酌セット
■浜松地ビール「HAMAMATSU BEER」全4種 各330ml
・ヴァイツェン×1
・アルト×1
・ヘレス×1
・シュヴァルツ×1
■ウィンナー全4種
・ポークウィンナー×4本(100g)
・唐辛子ソーセージ×4本(100g)
・ブラートブルスト×4本(100g)
・ビアシンケン×6枚(400g)
 「ご当地の美味しいお酒」と「ご当地自慢のグルメ」セット通販サイト【SAKEぐる】
「ご当地の美味しいお酒」と「ご当地自慢のグルメ」セット通販サイト【SAKEぐる】
日本各地のグルメ食材に相性の良い「ご当地のお酒」をセット。
北は北海道から南は沖縄まで、「ワイン&チーズ」「日本酒&ふく」「芋焼酎&鶏炭火焼」など 100セットを超えるランナップで、日本全国各地にあるグルメ食材に、それと相性の良い「ご当地のお酒」にスポットを当て、セットにしてお届けします。
埋もれた地方の美味しい産物をお届けするために、冷蔵品(チーズ、お肉、魚介など)もくわえ、美味しさ(お酒)、うまさ(自慢のグルメ)が、”ダブル+α”で楽しめます。
※「生産者のご紹介」コーナーでは、各地の酒蔵・ワイナリー(作り手)の想いを特集。
お酒が誕生するまでの紆余曲折や深い歴史もわかり、作り手の想いが詰まったお酒を味わいながら、グルメとともに、それが生まれた風景も楽しめる仕組みになっています。
うまいお酒とおいしいグルメを、その背景のロマンとともに存分に味わえるサイトです。
![]()
うまいお酒の最高の相棒、おいしいグルメ
全国にまだまだ知られていない隠れた“おいしさ”がいっぱい

 賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、
賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、まだ食べられるもの、使えるものをお買い得価格で提供するSDGsなサイト。
![]()
 「賞味期限間近」などのワケあり商品をお値打ち価格で販売している会員制の通販サイト。期間がたつほど安くなり、0円で手に入ることも。
「賞味期限間近」などのワケあり商品をお値打ち価格で販売している会員制の通販サイト。期間がたつほど安くなり、0円で手に入ることも。![]()
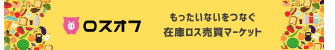 全国の在庫ロスを抱える「生産者・卸業者・販売者」と、「買い手」を直接つなぎ、特別価格で商品が購入できる在庫ロス販売マーケットです。
全国の在庫ロスを抱える「生産者・卸業者・販売者」と、「買い手」を直接つなぎ、特別価格で商品が購入できる在庫ロス販売マーケットです。
![]()
 未利用魚は、一般には知られていないので店先から敬遠されている魚の総称で、漁師さんの家で食べられるほかは、捨てられていた魚のことをいいます。市場に出回らなくなった、なんとももったいない魚などをご家庭にお届けしようというサブスクサイトです。
未利用魚は、一般には知られていないので店先から敬遠されている魚の総称で、漁師さんの家で食べられるほかは、捨てられていた魚のことをいいます。市場に出回らなくなった、なんとももったいない魚などをご家庭にお届けしようというサブスクサイトです。![]()
 「ロス(廃棄)になるパンをなくしたい!」
「ロス(廃棄)になるパンをなくしたい!」 パン屋さんで、まだ食べられるのにどうしても出てしまう廃棄せざるを得ないパンがrebakeの取り扱うロスパンです。
全国のパン屋さんとつなげるプラットホームサイトです。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2493dbad.68ff92e3.2493dbae.d9ad6498/?me_id=1237482&item_id=10002114&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faionline-japan%2Fcabinet%2Fdk01%2Fik-07new.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
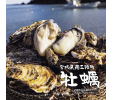














![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1dc76aa6.844ddcc9.1dc76aa7.6bcfe948/?me_id=1202364&item_id=10000057&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbaeren%2Fcabinet%2Fbin%2F07964133%2Fimgrc0115987801.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a844296.9bea3fb9.1a844297.02808163/?me_id=1335812&item_id=10001104&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbeer-the-world%2Fcabinet%2Frakuten9%2Fb123n2-500rakuten.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c896686.e06cc798.1c896687.263ec4c2/?me_id=1277065&item_id=10001905&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fissyusouden%2Fcabinet%2Fproducts%2Fbeer%2F03211469%2Fyonayona-set02.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c95b46d.3a92fac0.1c95b46e.2fe35f4a/?me_id=1200583&item_id=10001463&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjizakeshop%2Fcabinet%2F01023591%2Fcoedo12p.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c896686.e06cc798.1c896687.263ec4c2/?me_id=1277065&item_id=10017644&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fissyusouden%2Fcabinet%2F2021_01%2F2021_02%2F30000286set.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)
 全国各地の醸造家たちがこだわりぬいて造ったクラフトビール
全国各地の醸造家たちがこだわりぬいて造ったクラフトビール